
日本のコンテンツはなぜテロップが多用されるの?

こんにちは〜!
COTONです。
昨日は英語イマージョン学習の経過についてを投稿しました。
今日は、どんなものを観ているか具体的に書こうかな、と思ったのですが、直前で書きたいことが変わりました。
それに関連するテーマです。
アメリカの対談Youtubeチャンネルを見ていると、テロップがほぼないです。
サムネイルもすごくシンプルでカッコ良いですよね。
ちなみにテロップは和製英語であり、日本独自の放送用語です。
(和製英語ややこしいからやめてほしい。)
日本のYoutubeコンテンツは「話していることを文字にして表示させる」=テロップがあるものが良い編集、よく見かける一般的な動画、とされています。
テレビ番組もたくさんテロップが表示されます。(地上波を見ていないので最近の番組は分からない)
サムネイルもゴリゴリの文字が入っていてHSPからすると情報量が多くてうるさいです。(笑)
でも、アメリカの動画はとにかくスッキリしています。
いくつか参考を貼っておきます。
↑大好きなThe O.C.サマー役のレイチェル・ビルソンのYoutubeチャンネル。
↑大好きなかなりオススメの本、「スタンフォードの脳外科医が教わった人生の扉を開く最強のマジック(Amazon PRリンク) 」を書いたジェームズ・ドゥティさんが出ている動画
どちらもトーク中に文字は出ず、とてもシンプルです。
ではなぜ日本のコンテンツには、文字がたくさん入っているのでしょうか?
これが気になったので、今日はこれについて投稿することにします。
Table of Contents
日本のYouTube・テレビ番組でテロップが多用される理由
視覚優位な文化
どうやら日本人は、「文字」や「視覚情報」で理解をする傾向が強いようです。
話の内容を文字で補足することで理解が深まりやすく、音声だけよりも文字があるほうが安心感を持つ視聴者が多いみたいです。
これは確かに頷けます。
私は圧倒的に視覚優位タイプなので、目で見て理解する方が音より何倍も理解しやすく、動画から情報を得るのが苦手なタイプです。
同じ情報が、動画と文章で紹介されているのなら、間違いなく文章を読むタイプです。
日本人自体が、この「視覚優位タイプ」の人が多いということでしょうか。
優しさ
別の理由としては、高齢者や、聴覚障害の方にも情報を伝える配慮をしていると考えられます。
また、周囲が騒がしい環境(電車の中等)でも内容が理解できるようにするためでしょうか。
日本は電車で移動するので、耳よりも目で情報を得られるようにしているのですね。
アメリカは車移動が中心で、かなりの時間ポッドキャストを聞く習慣があると聞いた事があります。(本当かは知りません)
笑いや感情の演出
- 面白い発言、強調したい部分をテロップで目立たせることで「ここが笑いどころ」と示す
- 字の色、大きさ、フォントで感情のニュアンスを伝える演出効果
確かに文字があるのとないのとでは、面白さが違う気がします。
伝達文化の違い
日本では「間違いなく伝える」ことが重視される一方、アメリカでは「自然さ・臨場感」が重視されるそうです。
なるほど。。
アメリカのYouTube・テレビ番組にテロップがない理由
聴覚理解力が高く、字幕依存が少ない
英語話者は 母音・子音の聞き分けができ、音声理解への依存度が高いことと、 テロップを挿入する文化がそもそも育っていないらしいです。
アメリカの聴覚理解が日本よりも高いのは言語の違いからくるものですかね。
制作文化の違い
- テロップを入れる作業は時間・コストがかかる
- アメリカのYouTubeは Vlog・リアル系が主流で演出を最小化する傾向
そうですよね。
日本の動画って編集に時間がかかりそうというイメージです。
その視点からアメリカの動画を見ると、何も入ってないから楽やん?!と感じます。
聴覚障害者向けにはクローズドキャプションを使用
必要な場合は 視聴者側で字幕をオンにする方式(CC) が主流らしいです。
日本もこれでいいのでは?と思ってしまいますね。
私はスッキリした画面の方が好みです。
情報量が多いと疲れます。
「伝えたいことをすべて補足する」という文化が弱い
アメリカは 個人の解釈や感じ取り方を尊重する文化があり、「何を言ったのか100%伝える」より「視聴者が感じる」ことを重視する。
なるほど・・。
こういうところでも、文化の違いを感じる事ができますね。
結論
日本
- 文字文化・視覚優位文化
- 情報量が多く、正確な伝達を重視
- エンタメ・感情演出としてテロップ活用
アメリカ
- 聴覚理解文化・リアル感重視
- 字幕は必要な人がオンにする(CC文化)
- テロップは不要とされる
アメリカ人の聴覚理解力が日本人よりも高いのは、言語が関係しているからか
気になったのでChat GPTに聞いてみました。
結論から言うと、英語という言語の音声構造・教育環境・文化が「聴覚理解優位」を形成しやすいようです。
また、日本語の言語特性と文化背景が「視覚優位」を形成しやすいみたいですね。
英語
- 子音・母音の種類が多く、音声情報が単語識別に重要
- スペルと発音が一致しないため、 音で覚えることが重要
- 強勢・抑揚・リズムが意味区切りになる(ストレスタイミング言語)
- 単語ごとの意味識別に「音の差」が必要
→音声から意味を取る練習が日常的に行われる
日本語
- 母音・子音の種類が少なく音の区別が容易
- 音声だけでも意味理解可能だが、漢字・ひらがな・カタカナの視覚情報で補完する文化
- 音の抑揚より文法・助詞で文構造が決まる(モーラタイミング言語)
- 同音異義語が多く、文脈や漢字の視覚情報が理解を助ける
→視覚情報で意味を取る文化が発達
考察
英語は、単語ごとの意味識別に「音の差」が必要に対して、日本語は同音異義語が多く、文脈や漢字の視覚情報が理解を助けるということからも、英語と日本語の言語の違いが面白いです。
日本人は状況や文脈によって、何を言っているのか自然と汲み取るということを普段からしているのですね。
つまり、はっきり言うと、「発音自体を重視せず、視覚情報を補足したり、その時の状況を考慮して、発言を理解をしている」という事ですよね。
これはそのまま、日本人が英語を話すことが苦手、にも繋がりますね。
英語は、音=1単語とはっきり音の差が生じているので、音を習得すれば迷う事がない、ただし単語を無限に覚えなければならないな、と。
教育・文化の違い
アメリカ
- 授業や討論、発表で 聞き取って即座に返答する訓練が多い
- テレビ・ラジオ・ポッドキャストの利用率が高く、音声情報が生活に密着
日本
- 黒板・プリント・文字教材が多く、視覚で学ぶ文化
- 書く・読むの時間が長く、音声で理解する訓練が少ない
- バラエティ番組もテロップで補う文化がある
アメリカは討論のイメージがありますね。
日本の授業は、黒板に書かれたものをノートに写して、授業中ほとんど声を出す事がなく終わったりしますよね。
今の小学校の授業参観に行くと、自分が受けていた授業より、とても楽しそうです。
授業の最後にパソコンで、今日習ったことに関する問題がクイズ形式(早押し)で出題され、正解率や速度のランキングが出たりして楽しそうでした。
バラエティ番組も必ずテロップが入っているし、確かにそれに慣れています。
結論
言語の特性が「英語圏で聴覚理解優位」「日本で視覚理解優位」を育てている。
アメリカ人の「聴覚理解力が高い」のではなく、
- 英語の聴覚情報処理が重要な言語特性
- 教育・文化が音声理解の機会を増やしている
ことが理由だそうです。
教育の仕方がかなり影響してそうな感じですね。
私は読書が大好きなのですが、視覚優位な人は本(文字情報)から情報を取り入れるのがラク・楽しいらしく、音声学習が苦手で、聞き逃すことが多いようです。
先ほども書きましたが、同じ情報があるとしたら、動画と本では本を選びます。
特に私は、小さな時から本に触れていて、たくさんの本を読んできたので、その結果として、文字情報を使った情報処理がさらに得意になったという面もありそうです。
- 小さい頃から本を読む習慣が強制的についた場合は視覚優位傾向が育つことはある
- しかし完全な聴覚優位・身体運動優位の人は「本を読むこと自体が苦痛」となり習慣化しづらいため、根本の優位感覚が変わることはあまりない
ちなみに息子は、聴覚優位タイプで、ほとんど本を読みませんし、文章問題等が苦手でした。
3年生くらいの時かな?
一度、「今日は学校で本を読んだよ!」と言うので、嬉しくて、どんな本を読んだの!?とテンションが上がって聞くと、AIがテーマの科学のお話だというではありませんか。
どんな内容だったかストーリーを言ってもらうと、よく分からない部分はあるものの、一応読んだストーリーを覚えて話していました。
すごい!と思って、色々聞いてみると、今すごく流行っている科学のサバイバルシリーズ、漫画でした。
最初はちょっとがっかりしたものの、私自身も漫画はたくさん読んできたので、漫画ももちろん良い!
何か読むきっかけになってくれたことが嬉しかったです。
最後に、ちょっと話が逸れてしまいますが、(いつも逸れるのですが)
息子は今5年生なのですが、社会の宿題だよと言って持って帰ってきたプリントが、国語のようなストーリーが書いてあって、問題に答える形式でした。
「え、これ社会なの!?めちゃくちゃ面白いやん!」
気になった私はプリントに出てくるタイトルとかで検索しまくって見つけました。
これでした。↓
こんなドリル私が小学校の時にあったら楽しかっただろうな〜
私は社会科がかなり苦手です。
私の方がテンションが上がっていると、先生から返された後に「ママこのプリント好きなんやったらあげるわ」と言ってくれました。
いや、いらんねんけど。
という訳で今日はここまでです。
また明日、お会いしましょう!
良い1日を。


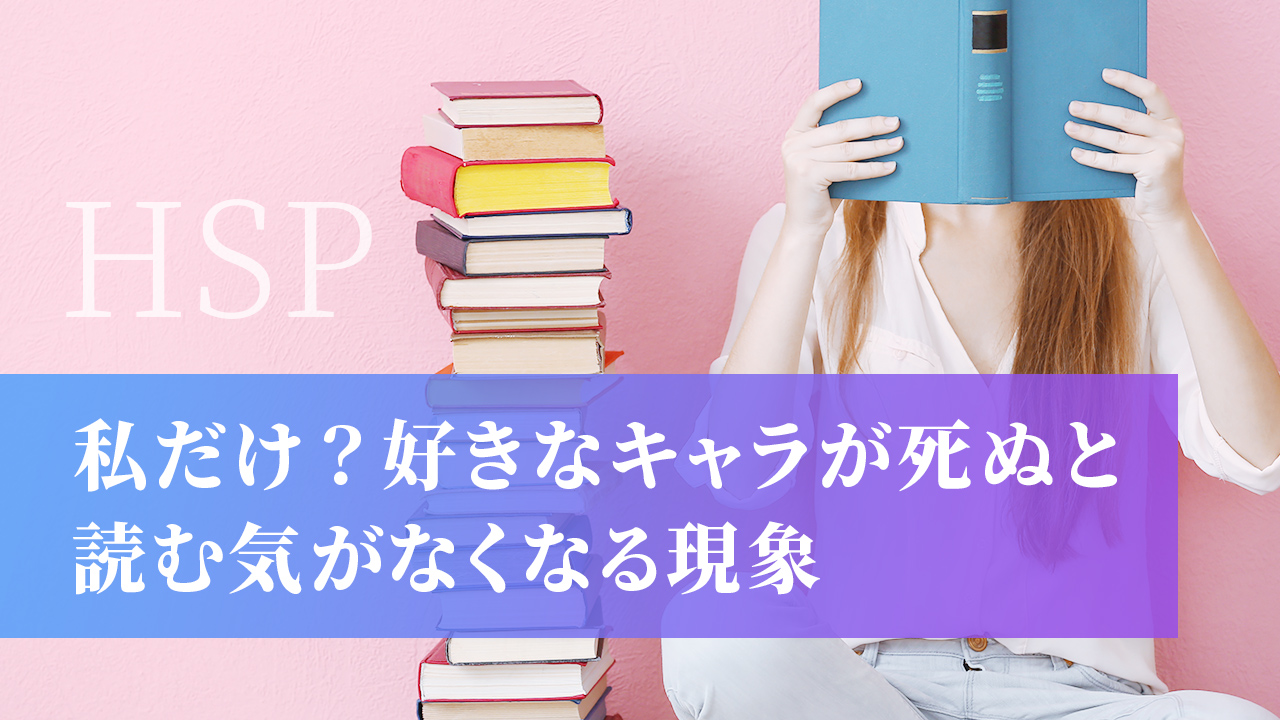
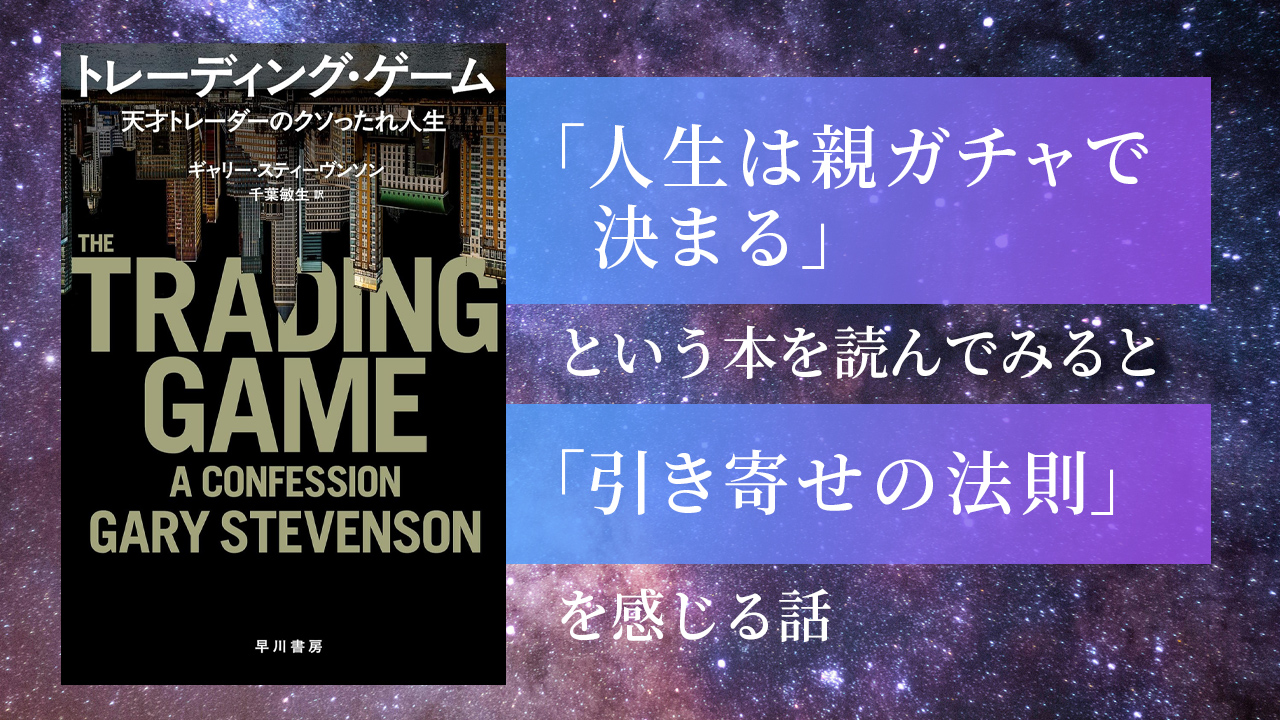
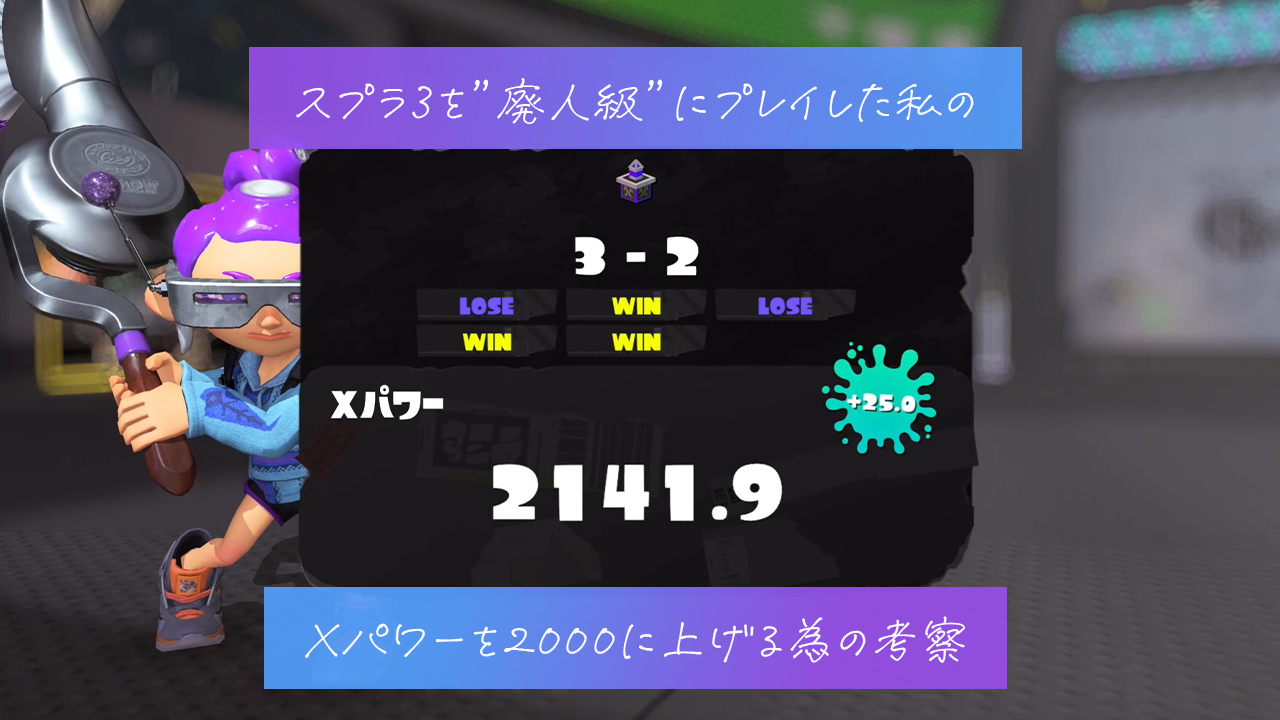
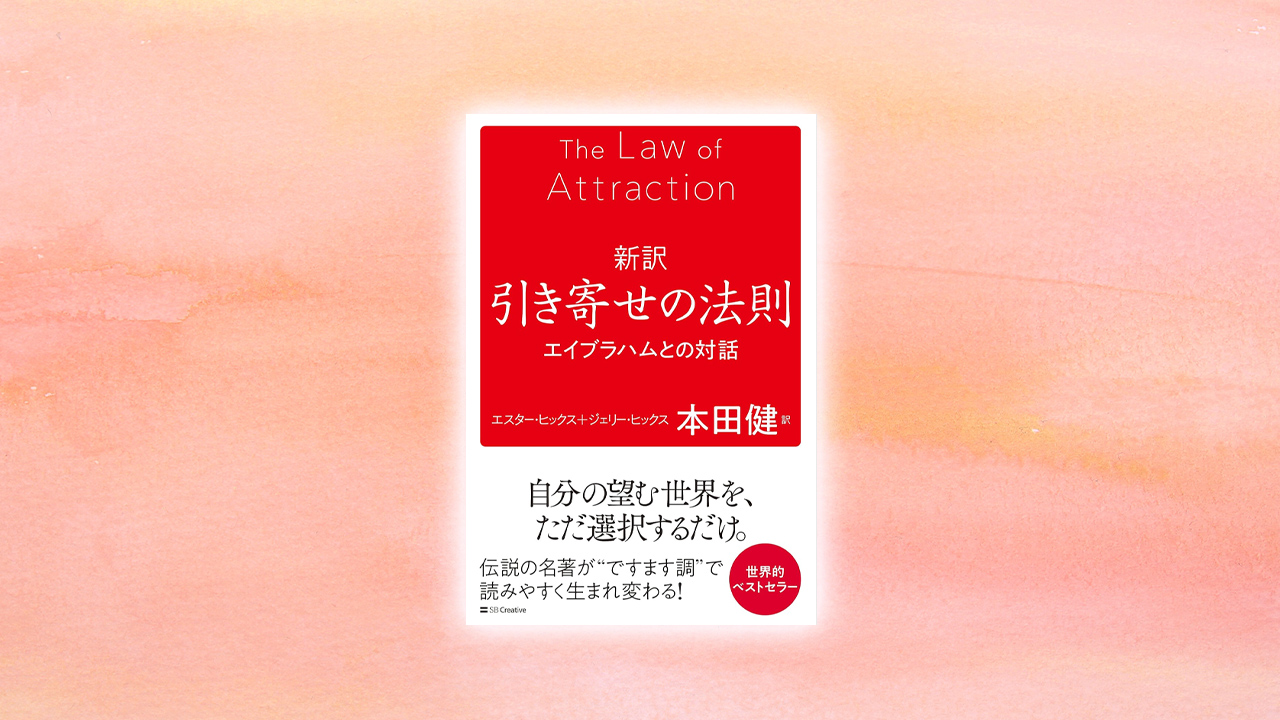
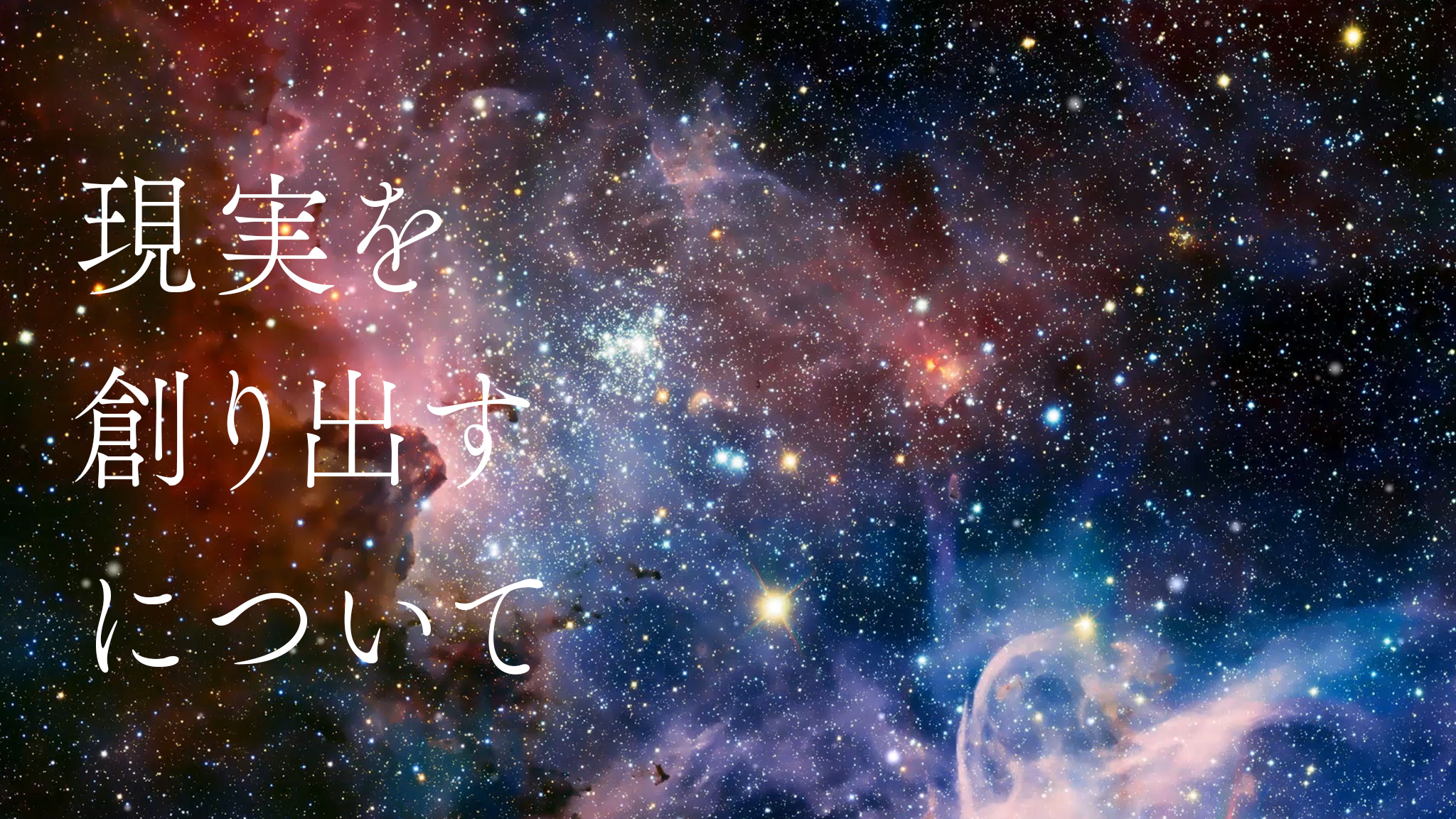
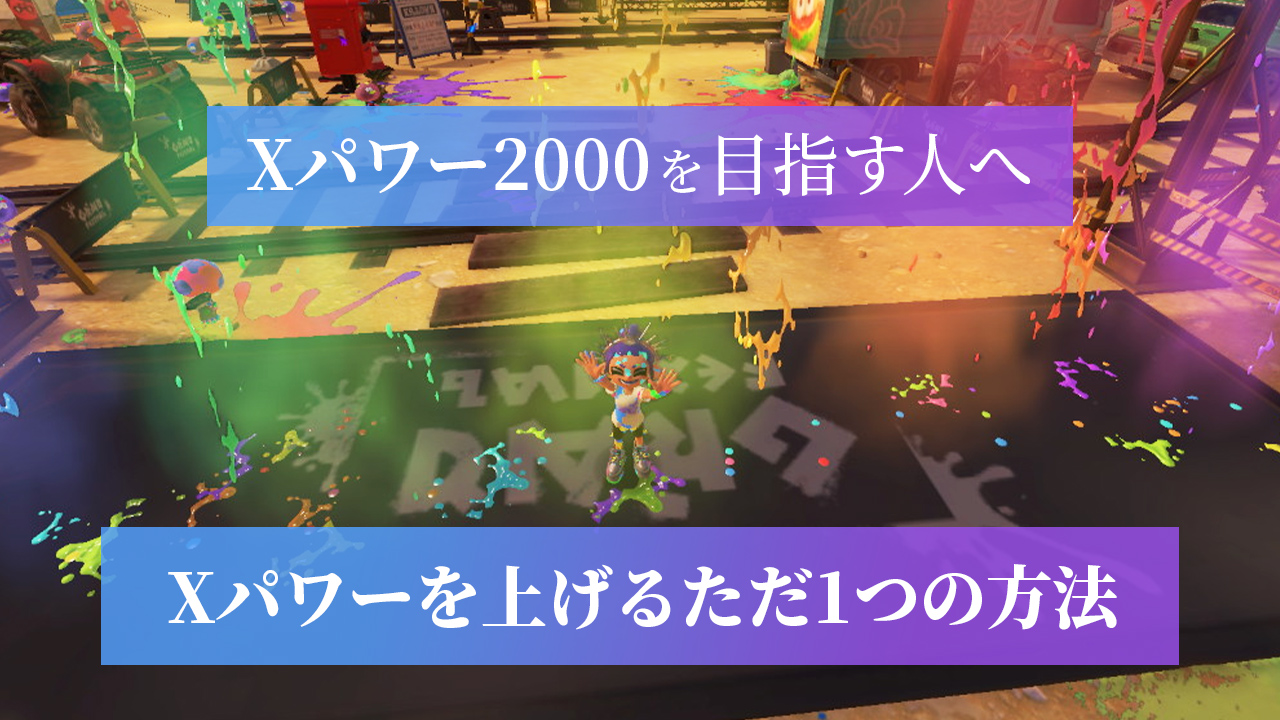
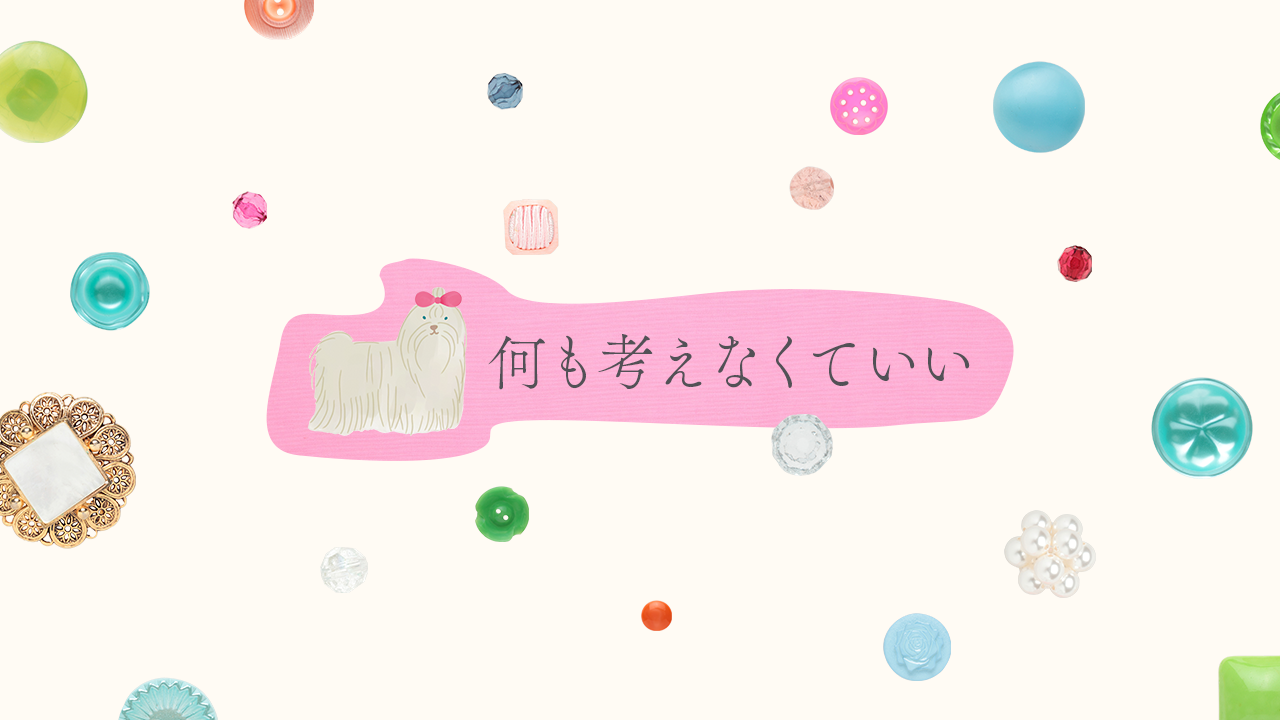
コメントを残す